2006年12月03日
「育児に大切なこと、学びませんか?」のお知らせ
「育児に大切なこと、学びませんか?」
生まれてきたことに感謝し、自分を大切にする心を育てることや家族力の強化・支援を行う
”あぷりこっと☆シープ”が、育児に関する勉強会を開催します。
”あぷりこっと☆シープ”は、クリスタルビルにある男女共同参画センターや生活創造センターにボランティア登録している、育児支援グループです。
今回の進行役は、”育児休業案内人”「青い夜」さんと、"タッピング・タッチ種まき保育士”「山羊」の二名です。
「青い夜」さんは、育児休業のエキスパートの社会保険労務士さんです。
私は、心の相互ケア「タッピング・タッチ」を担当します。
今回、グループとして始めての活動になります。
どこで・いつ・何時から?
はい、来週の土曜日12月9日、午後2時~4時まで、場所は、灘区にある旧灘区役所三階「防災研究室」です。
みなさまとご縁がつながれば、嬉しく想います。

生まれてきたことに感謝し、自分を大切にする心を育てることや家族力の強化・支援を行う
”あぷりこっと☆シープ”が、育児に関する勉強会を開催します。
”あぷりこっと☆シープ”は、クリスタルビルにある男女共同参画センターや生活創造センターにボランティア登録している、育児支援グループです。
今回の進行役は、”育児休業案内人”「青い夜」さんと、"タッピング・タッチ種まき保育士”「山羊」の二名です。
「青い夜」さんは、育児休業のエキスパートの社会保険労務士さんです。
私は、心の相互ケア「タッピング・タッチ」を担当します。
今回、グループとして始めての活動になります。
どこで・いつ・何時から?
はい、来週の土曜日12月9日、午後2時~4時まで、場所は、灘区にある旧灘区役所三階「防災研究室」です。
みなさまとご縁がつながれば、嬉しく想います。

2006年11月25日
「子育て」と「介護」の共通の”しんどさ”
「介護」をしていて一番辛いのは、物理的な大変さよりも、本当は「介護」という場面に映し出される「自分のおぞましさ」」を見なければいけないことだ。
(中略)
私は自分のことを「優しい人間だ」と思ってきたし、人からもよく言われてきたのだ。
ところが「介護」をしていると、優しくない自分がむき出しになる。
(中略)
「ああ、なんて、私っていやな人間なんだろう。ああ、エゴイズムの塊だあ」
私は自分の中にある悪意に愕然として、そういう自分が許せなくて、深夜に一人、号泣したりしたのだ。
久田 恵さんの「家族を卒業します」の一文です。
私はこの文章を読んで、「育児」のしんどさとの共通点を思いました。
子育てを経験して「自分って、思ったより子どもが好きじゃないんだ」と気が付いたという声も聞きます。
そして、それに気が付いたときにショックだったと。。。
「母親は無条件に子どもを愛するものだ」という一般的な真理が、そういう心をより苦しめることも珍しくありません。
「介護地獄」を作っているのは、福祉がひどいせいだ。という声を頻繁に聞くけれど、
「介護」にかかわる私たちのエゴイズムを克服する価値観を、共に見つけ出す努力もしないままに、そのことに苦しみもしないで、皆のいやなことを肩代わりするだけの思想のない施策ばかりを求めて、結局は自分たちの日々をシアワセじゃないものにしてしまうのではないかしら?
育児の問題もそうだと思います。
働くお母さんにも子育てしやすい施策や環境を整えてあげるだけでは、「育児の悩み」は解決しないと思います。
育児をする上での本当の「心のしんどさ」を、共感・理解し見守り寄り添う”温かい視点”がベースにあって初めて、そういう施策が生きてくるのだと思います。
「介護」も「育児」も、自分と向き合う作業という意味では共通しています。
心がしんどくなったとき、どうか自分を責めないでください。
「ありのまま」の自分を受け入れること・・・いつも心に留めておきたいですね。

(中略)
私は自分のことを「優しい人間だ」と思ってきたし、人からもよく言われてきたのだ。
ところが「介護」をしていると、優しくない自分がむき出しになる。
(中略)
「ああ、なんて、私っていやな人間なんだろう。ああ、エゴイズムの塊だあ」
私は自分の中にある悪意に愕然として、そういう自分が許せなくて、深夜に一人、号泣したりしたのだ。
久田 恵さんの「家族を卒業します」の一文です。
私はこの文章を読んで、「育児」のしんどさとの共通点を思いました。
子育てを経験して「自分って、思ったより子どもが好きじゃないんだ」と気が付いたという声も聞きます。
そして、それに気が付いたときにショックだったと。。。
「母親は無条件に子どもを愛するものだ」という一般的な真理が、そういう心をより苦しめることも珍しくありません。
「介護地獄」を作っているのは、福祉がひどいせいだ。という声を頻繁に聞くけれど、
「介護」にかかわる私たちのエゴイズムを克服する価値観を、共に見つけ出す努力もしないままに、そのことに苦しみもしないで、皆のいやなことを肩代わりするだけの思想のない施策ばかりを求めて、結局は自分たちの日々をシアワセじゃないものにしてしまうのではないかしら?
育児の問題もそうだと思います。
働くお母さんにも子育てしやすい施策や環境を整えてあげるだけでは、「育児の悩み」は解決しないと思います。
育児をする上での本当の「心のしんどさ」を、共感・理解し見守り寄り添う”温かい視点”がベースにあって初めて、そういう施策が生きてくるのだと思います。
「介護」も「育児」も、自分と向き合う作業という意味では共通しています。
心がしんどくなったとき、どうか自分を責めないでください。
「ありのまま」の自分を受け入れること・・・いつも心に留めておきたいですね。

2006年11月03日
子育て何でもぶっちゃけ!その②
「育児に疲れたとき SOSを送れる人がいるか どうか」
これは、とても大切なポイントだと思います。
私は一人目を出産した時、まだ20代半ばでした。
実家の母は持病を抱え、入退院を繰り返していました。
出産時、一時的に実家に帰りましたが、結局子どもが生まれてまもなく母が入院。
結果的に、全て自分でしなければいけなくなりました。
37週入ってすぐに生まれた娘は、2500g少し超えたくらいの小柄な赤ちゃんだったことも手伝って、
母乳を飲むチカラが弱かったようです。
良く夜泣きをしました。
一人夜中に、泣く娘を抱いていると、とてつもない孤独感と不安が襲って来たのを覚えています。
そんなある日、民間の「育児相談」があることを知り、思い切って電話をしました。
ところが・・・・・
・・・・・・・返ってきた言葉の一つ一つが「教科書的」だったのです。
相手は一方的に話をすると、そのまま電話を切ってしまいました。
もちろん、相談員さんには親身になってくださる方も多くおられます。
たまたま、その時は そういう方に当たってしまったのでしょう。
ますます落ち込んで「誰に相談したらええの?」と自問自答の日々が続いたのです。
それでどうしたかというと・・・・・
病院に行った時に、看護師さんに相談したり、たまたま知り合ったお母さんに話を聞いてもらったりして、何とか乗り切ることができました。
親が相談できる状態・状況であれば、一番心強いと思いますが、そうでない場合。
「話せる相手」というのは、とても重要になってくると思います。
育児はもちろん、育児書通りには行きません。
育児書に書いてある情報が役に立つ場合もあれば、逆に混乱する場合もあると思います。
氾濫する情報の中で、いかに「子どもの個性に焦点を当てたオリジナルな子育て」ができるか
親の心一つだと思います。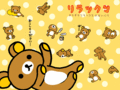
これは、とても大切なポイントだと思います。
私は一人目を出産した時、まだ20代半ばでした。
実家の母は持病を抱え、入退院を繰り返していました。
出産時、一時的に実家に帰りましたが、結局子どもが生まれてまもなく母が入院。
結果的に、全て自分でしなければいけなくなりました。
37週入ってすぐに生まれた娘は、2500g少し超えたくらいの小柄な赤ちゃんだったことも手伝って、
母乳を飲むチカラが弱かったようです。
良く夜泣きをしました。
一人夜中に、泣く娘を抱いていると、とてつもない孤独感と不安が襲って来たのを覚えています。
そんなある日、民間の「育児相談」があることを知り、思い切って電話をしました。
ところが・・・・・
・・・・・・・返ってきた言葉の一つ一つが「教科書的」だったのです。
相手は一方的に話をすると、そのまま電話を切ってしまいました。
もちろん、相談員さんには親身になってくださる方も多くおられます。
たまたま、その時は そういう方に当たってしまったのでしょう。
ますます落ち込んで「誰に相談したらええの?」と自問自答の日々が続いたのです。
それでどうしたかというと・・・・・
病院に行った時に、看護師さんに相談したり、たまたま知り合ったお母さんに話を聞いてもらったりして、何とか乗り切ることができました。
親が相談できる状態・状況であれば、一番心強いと思いますが、そうでない場合。
「話せる相手」というのは、とても重要になってくると思います。
育児はもちろん、育児書通りには行きません。
育児書に書いてある情報が役に立つ場合もあれば、逆に混乱する場合もあると思います。
氾濫する情報の中で、いかに「子どもの個性に焦点を当てたオリジナルな子育て」ができるか
親の心一つだと思います。
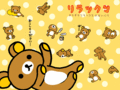
2006年11月01日
子どもの遊び
「米で鬼ごっこ禁止拡大」
アメリカの小学校で伝統的な子どもたちの遊び「タグ(鬼ごっこ)」を禁止する動きが目立っているそうです。
「子どもの怪我防止」か「外遊びによる健全育成」か、で議論を呼んでいるとか。
この背景には、怪我をした場合の責任を回避したいという、”教育現場の保身”があると、記事は語っています。
遊びに夢中になった子どもたちがぶつかったり、タッチではなく相手を叩くなど、怪我につながりかねないというのが禁止の理由だそうです。
子どもは、いうまでもなく「遊び」を通じていろいろなことを学びます。
どこまでしたら「危険」で、どこまでなら「安全」かなど、身体を使った遊びを通じて学んでいくのです。
鬼ごっこは、相手との駆け引きや瞬発力などを養うのに最適な遊びだと思います。
また走り回るので、ストレス解消になったり、体力もつくでしょう。
何でも「危険だから」ということで避けていたら、本当に危険なこととの境界がわからなくなり、その方が余計に”危険”だと思います。
大人の都合で、「生きるチカラ」を育む”遊び”を禁止するアメリカの一部の風潮に、危機感を覚えます。
そういえば、昔は良く見かけた”木のぼり”をする子どもの姿も、今はほとんど見なくなりました。
・・・・・・・・「見守る」子育ての難しさを、”遊び”の中にも感じます。
アメリカの小学校で伝統的な子どもたちの遊び「タグ(鬼ごっこ)」を禁止する動きが目立っているそうです。
「子どもの怪我防止」か「外遊びによる健全育成」か、で議論を呼んでいるとか。
この背景には、怪我をした場合の責任を回避したいという、”教育現場の保身”があると、記事は語っています。
遊びに夢中になった子どもたちがぶつかったり、タッチではなく相手を叩くなど、怪我につながりかねないというのが禁止の理由だそうです。
子どもは、いうまでもなく「遊び」を通じていろいろなことを学びます。
どこまでしたら「危険」で、どこまでなら「安全」かなど、身体を使った遊びを通じて学んでいくのです。
鬼ごっこは、相手との駆け引きや瞬発力などを養うのに最適な遊びだと思います。
また走り回るので、ストレス解消になったり、体力もつくでしょう。
何でも「危険だから」ということで避けていたら、本当に危険なこととの境界がわからなくなり、その方が余計に”危険”だと思います。
大人の都合で、「生きるチカラ」を育む”遊び”を禁止するアメリカの一部の風潮に、危機感を覚えます。
そういえば、昔は良く見かけた”木のぼり”をする子どもの姿も、今はほとんど見なくなりました。
・・・・・・・・「見守る」子育ての難しさを、”遊び”の中にも感じます。

2006年10月31日
イノチの大切さ
<命>
命はとても大切だ
人間が生きるための電池みたいだ
でも電池はいつかは切れる
命もいつかはなくなる
電池はすぐにとりかえられるけれど
命はそう簡単にはとりかえられない
何年も何年も
月日がたってやっと
神様から与えられるものだ
命がないと人間は生きられない
でも「命なんていらない」と言って
命を無駄にする人もいる
まだたくさん命が使えるのに
そんな人を見ると悲しくなる
命は休むことなく働いているのに
だから、私は命が疲れたと言うまで
せいいっぱい生きよう
(10月29日付けの産経新聞に掲載されていました)
これは、神経細胞胞腫という難病にかかっていた11歳の女の子が書いた詩です。
彼女は、この詩を書いた半年後に亡くなったそうです。
この詩を通じて少女が伝えたかった”想い”。。。
生きている私たち一人一人が、しっかり受け止めて日々の生活に生かさなければいけないと、最近のニュースを通じて思います。

社会の枠にはまらなくとも、他人から何と言われうようと、与えられた”イノチ”を全うする「生きるチカラ」を、子どもに伝えること。。。何があっても、親は子どもを見捨てないこと。。。
それが、この世にイノチを与えた親の使命だと、改めて感じます。
命はとても大切だ
人間が生きるための電池みたいだ
でも電池はいつかは切れる
命もいつかはなくなる
電池はすぐにとりかえられるけれど
命はそう簡単にはとりかえられない
何年も何年も
月日がたってやっと
神様から与えられるものだ
命がないと人間は生きられない
でも「命なんていらない」と言って
命を無駄にする人もいる
まだたくさん命が使えるのに
そんな人を見ると悲しくなる
命は休むことなく働いているのに
だから、私は命が疲れたと言うまで
せいいっぱい生きよう
(10月29日付けの産経新聞に掲載されていました)
これは、神経細胞胞腫という難病にかかっていた11歳の女の子が書いた詩です。
彼女は、この詩を書いた半年後に亡くなったそうです。
この詩を通じて少女が伝えたかった”想い”。。。
生きている私たち一人一人が、しっかり受け止めて日々の生活に生かさなければいけないと、最近のニュースを通じて思います。

社会の枠にはまらなくとも、他人から何と言われうようと、与えられた”イノチ”を全うする「生きるチカラ」を、子どもに伝えること。。。何があっても、親は子どもを見捨てないこと。。。
それが、この世にイノチを与えた親の使命だと、改めて感じます。
2006年10月30日
傷ついた一言
子どもの頃に他人から言われて「傷ついた一言」はありますか?
誰でも大なり小なりあるのではないでしょうか。
「ちょっとした一言が招く”心のいじめ”confidenceランキング&ニュース」に掲載されていたランキングから紹介します。
最も多かったのは容姿に関する”からかい”です。
「でぶ」「たらこ唇」「ちび」「ブス」「あごがしゃくれてる」「歯が出てる」など、本人にはどうしようもないことを指摘されると、傷つきます。
本人がコンプレックスに思っていることが多いので、なおのことですね。
「見た目にわかることだから、気にすることない。」というのは、当事者でない者の勝手な思い込みで、その人の主観で見た目をストレートに言うのはタブーだと思います。
私が最も気になった一言は「うざい」です。
この言葉は、相手の存在そのものを否定する、立派な言葉の暴力です。
「死ね」という言葉は、言語道断ですね。
同様に、「きもい」「きしょい」「ムカつく」など・・・人権を無視した言葉を人に向かって言う権利は誰にもありません。
私は親がまず、小さい時から子どもの「言葉使い」をちゃんと正すことが必要だと思います。
「どういう言葉を使ってはいけないか」
「どういう言葉が人を傷つけるか」
事在るごとに、子どもと話し合うことが大切だと思うのです。
でも、肝心の親がその言葉を日常的に使っていたり、親も言葉で子どもを傷つけている場合があるので、問題はより複雑です。
次に親から言われて傷ついた言葉として、
「お姉ちゃんは勉強ができるのに、あなたは・・・」
「お父さんに似て ムカつく」
「お母さんと妹は美人だね」
極めつけは、
「あんたなんて 産まなければ良かった」」「誰の子かわからん」
言葉の暴力は、目に見えないだけに深く・強く・そしていつまでも「心の傷」として残るのだと思います。
「言葉」はチカラ・・・
暴力としてのチカラに変えるのではなく、その一言が「生きるチカラ」になるような言葉を、子どもに多く伝えたいと、心から思います。
・・・・児童養護施設で出会った子どもたちを思い出し、胸が痛みました。
誰でも大なり小なりあるのではないでしょうか。
「ちょっとした一言が招く”心のいじめ”confidenceランキング&ニュース」に掲載されていたランキングから紹介します。
最も多かったのは容姿に関する”からかい”です。
「でぶ」「たらこ唇」「ちび」「ブス」「あごがしゃくれてる」「歯が出てる」など、本人にはどうしようもないことを指摘されると、傷つきます。
本人がコンプレックスに思っていることが多いので、なおのことですね。
「見た目にわかることだから、気にすることない。」というのは、当事者でない者の勝手な思い込みで、その人の主観で見た目をストレートに言うのはタブーだと思います。
私が最も気になった一言は「うざい」です。
この言葉は、相手の存在そのものを否定する、立派な言葉の暴力です。
「死ね」という言葉は、言語道断ですね。
同様に、「きもい」「きしょい」「ムカつく」など・・・人権を無視した言葉を人に向かって言う権利は誰にもありません。
私は親がまず、小さい時から子どもの「言葉使い」をちゃんと正すことが必要だと思います。
「どういう言葉を使ってはいけないか」
「どういう言葉が人を傷つけるか」
事在るごとに、子どもと話し合うことが大切だと思うのです。
でも、肝心の親がその言葉を日常的に使っていたり、親も言葉で子どもを傷つけている場合があるので、問題はより複雑です。
次に親から言われて傷ついた言葉として、
「お姉ちゃんは勉強ができるのに、あなたは・・・」
「お父さんに似て ムカつく」
「お母さんと妹は美人だね」
極めつけは、
「あんたなんて 産まなければ良かった」」「誰の子かわからん」
言葉の暴力は、目に見えないだけに深く・強く・そしていつまでも「心の傷」として残るのだと思います。
「言葉」はチカラ・・・
暴力としてのチカラに変えるのではなく、その一言が「生きるチカラ」になるような言葉を、子どもに多く伝えたいと、心から思います。
・・・・児童養護施設で出会った子どもたちを思い出し、胸が痛みました。

2006年10月29日
子どもを叱る その②
昨日の続きです。
②できる限り、感情を交えないこと
良く言われることですが、”怒る”のではなく”叱る”ことを忘れない。
これはある意味、とても難しいですね。
怒るときは、どうしても感情的になってしまいます。
子どもも、感情に任せて怒っているのか、本当に自分のことを心配して叱っているのか、本能的に察知するようで、親が感情的になっている時は、結構効き目がないことが多いように思います。
③子どもの目の高さまで背をかがめる
ちゃんと目線を高さに合わせ、目を見て言います。
とても大切な視点ですね、
”目を見て話す”というのに、大人も子どもも関係ないですね。
上からモノを言われると、とても威圧感があると思います。
④「いけないこと」をした理由を聞く
なぜそんな行動をしたのか、聞き出せる状態であれば、その言い分を聞いてあげましょう。
その時「なんで そんなことしたん?!」と、怒ったように聞かないようにすることは大事ですね。
感情的になっている時は、どうしても「なんでなん?」と、”問い詰めて”しまいがちですが、親も一呼吸置くようにしたいですね。
⑤叱られた理由をわからせる
どうして叱れているのか、本人に分かるようにはっきりと言います。
子どもにも、納得できる言い方・話し方が大切ですね。
そのためには、感情的にならず、筋道立てて、分かりやすいように話すことが必要になってきます。
親も”訓練”が必要かも?
⑥叱った後のフォローをする
叱り終わったら気持ちをきりかえて、「お母さん(お父さん)は、あなたが大好きよ」と言って、抱っこしたり背中をなでたりします。
このフォローが一番大切なような気がします。
子どもは、叱られると「嫌われているんじゃないか」と、不安になりますが、後でちゃんと
「叱ること」と「あなたを嫌いなこと」は、一緒ではないことを、スキンシップを通じて子どもに伝えると、
子どもはとても安心しますね。
虐待されている子どもは、常にこの「嫌われている」という不安に怯えています。
だから、必要以上に親の機嫌を取ったり、甘えたりします。
⑦叱らなければいけない時は、必ず同じように叱る
同じように悪い事をしたのに叱ったり叱らなかったりすると、良いことなのか悪いことなのか、子どもの中で混乱が起こってしまいます。
これも親が意識して気を付けないといけないことですね。
”一貫性”を持たせることは、母親と父親、両方ともに必要です。
母親と父親の意見や方針が違うと、子どもは指標」を失ってしまい、良いことなのか悪いことなのか判断がつかなくなります。
これだけ見ても、子育てって「親育て」なんだとつくづく思いますね。
私も基本的なことはちゃんと子どもに伝えたつもりですが、成長するにつれて、いろいろややこしい問題に遭遇したとき、「果たしてこれで良かったのか」と、自問自答することも多々ありました。
一生育自ですね。
②できる限り、感情を交えないこと
良く言われることですが、”怒る”のではなく”叱る”ことを忘れない。
これはある意味、とても難しいですね。
怒るときは、どうしても感情的になってしまいます。
子どもも、感情に任せて怒っているのか、本当に自分のことを心配して叱っているのか、本能的に察知するようで、親が感情的になっている時は、結構効き目がないことが多いように思います。
③子どもの目の高さまで背をかがめる
ちゃんと目線を高さに合わせ、目を見て言います。
とても大切な視点ですね、
”目を見て話す”というのに、大人も子どもも関係ないですね。
上からモノを言われると、とても威圧感があると思います。
④「いけないこと」をした理由を聞く
なぜそんな行動をしたのか、聞き出せる状態であれば、その言い分を聞いてあげましょう。
その時「なんで そんなことしたん?!」と、怒ったように聞かないようにすることは大事ですね。
感情的になっている時は、どうしても「なんでなん?」と、”問い詰めて”しまいがちですが、親も一呼吸置くようにしたいですね。
⑤叱られた理由をわからせる
どうして叱れているのか、本人に分かるようにはっきりと言います。
子どもにも、納得できる言い方・話し方が大切ですね。
そのためには、感情的にならず、筋道立てて、分かりやすいように話すことが必要になってきます。
親も”訓練”が必要かも?
⑥叱った後のフォローをする
叱り終わったら気持ちをきりかえて、「お母さん(お父さん)は、あなたが大好きよ」と言って、抱っこしたり背中をなでたりします。
このフォローが一番大切なような気がします。
子どもは、叱られると「嫌われているんじゃないか」と、不安になりますが、後でちゃんと
「叱ること」と「あなたを嫌いなこと」は、一緒ではないことを、スキンシップを通じて子どもに伝えると、
子どもはとても安心しますね。
虐待されている子どもは、常にこの「嫌われている」という不安に怯えています。
だから、必要以上に親の機嫌を取ったり、甘えたりします。
⑦叱らなければいけない時は、必ず同じように叱る
同じように悪い事をしたのに叱ったり叱らなかったりすると、良いことなのか悪いことなのか、子どもの中で混乱が起こってしまいます。
これも親が意識して気を付けないといけないことですね。
”一貫性”を持たせることは、母親と父親、両方ともに必要です。
母親と父親の意見や方針が違うと、子どもは指標」を失ってしまい、良いことなのか悪いことなのか判断がつかなくなります。
これだけ見ても、子育てって「親育て」なんだとつくづく思いますね。
私も基本的なことはちゃんと子どもに伝えたつもりですが、成長するにつれて、いろいろややこしい問題に遭遇したとき、「果たしてこれで良かったのか」と、自問自答することも多々ありました。
一生育自ですね。

2006年10月28日
子どもを叱る その①
子どもの叱り方って、結構難しいと感じたことはありませんか?
良く混乱してしまうことは、
「したこと(悪いこと)を叱ること」と「子どもの人格を否定」してしまうことだと思います。
例えば、ひじをつくなど、食事のマナーを注意した時に、それだけを叱れば(注意すれば)いいのに
それが何故か「ほんとに行儀が悪い。誰に似たんだろうね。。。」などと言うのは、本題がずれています。
子どものした悪いことを認識させることはもちろん大切ですが、それが発展して、子どもの人格や存在を否定しまうと、子どもの心は傷つきます。
私も経験ありますが、というか、子どもが小さい時は、その反省の繰り返しでした。
子どものしたことだけを、”短くその場で”叱ればいいものを、ふっと思い出した過去のことを持ち出してきたり、子どもの性格を否定するようなことを言ってしまったり。。。
子どもの悲しむ顔を見て初めて反省して。。。
「叱り方」は、本当に難しいと思いました。
<効果的な叱り方 七か条>から 順番にご紹介したいと思います。
①その場で叱ること
時間を置くと、子どもは何を叱られているのか分かりません。
「そういえば、朝こんなことがあったけど、それはね・・・」と、夜に叱っても、子どもも何のことか忘れてしまっているでしょう。
覚えていたとしても、右から左で、叱る効果はないと思います。
私もたまに、思い出して子どもに注意することがありますが、もう高校生になった子どもからは
「何いうとん?それ、いつのこと?」と一言かわされて、終わりです(汗)
何でも「その場」が効果的です。
ということで、また次回に続きます。
良く混乱してしまうことは、
「したこと(悪いこと)を叱ること」と「子どもの人格を否定」してしまうことだと思います。
例えば、ひじをつくなど、食事のマナーを注意した時に、それだけを叱れば(注意すれば)いいのに
それが何故か「ほんとに行儀が悪い。誰に似たんだろうね。。。」などと言うのは、本題がずれています。
子どものした悪いことを認識させることはもちろん大切ですが、それが発展して、子どもの人格や存在を否定しまうと、子どもの心は傷つきます。
私も経験ありますが、というか、子どもが小さい時は、その反省の繰り返しでした。
子どものしたことだけを、”短くその場で”叱ればいいものを、ふっと思い出した過去のことを持ち出してきたり、子どもの性格を否定するようなことを言ってしまったり。。。
子どもの悲しむ顔を見て初めて反省して。。。
「叱り方」は、本当に難しいと思いました。
<効果的な叱り方 七か条>から 順番にご紹介したいと思います。
①その場で叱ること
時間を置くと、子どもは何を叱られているのか分かりません。
「そういえば、朝こんなことがあったけど、それはね・・・」と、夜に叱っても、子どもも何のことか忘れてしまっているでしょう。
覚えていたとしても、右から左で、叱る効果はないと思います。
私もたまに、思い出して子どもに注意することがありますが、もう高校生になった子どもからは
「何いうとん?それ、いつのこと?」と一言かわされて、終わりです(汗)
何でも「その場」が効果的です。
ということで、また次回に続きます。

2006年10月27日
自分の足でしっかり立つ
「育児・育自」はわかるけれど、「育地」って???
カテゴリーを見て、「何だこれは?」って思われた方も多いと思います。
もちろん造語ですが、意味があります。
そのまま読むと「地面を育てる」
これだけでは、ますます何のことかわかりません。
「地面」って、大地のことです。
自分がしっかり立つ足元です。
「子育てしながら、自分も育ち、そして、自分の足元しっかり固めて、子どもや自分にどんな嵐が来ようと倒れない強い根元を作る」
・・・・そんな意味が込められています。
私はとても弱い木でした。
夫という支木がなければ、一人で立っていられない依存心の強い木でした。
「子育て」も、二人でしている間はあまり不安はありませんでした。
ある日急に支木が外れた瞬間、いろんな嵐がやってきたのです。
私は子どもがある程度の年齢になっていましたが、これがもし、子どもが生まれてすぐだったら、子どもがまだ小さかったら。。。と思うと、どんなに心細く、不安になるか。。。思っただけで胸が痛みます。
「大地にしっかり立つ」ために大切なこと。。。それは「自分を好きになること」
どんな自分も、全て「ありのまま」受け入れることができて、初めて大地の根っこは奥深く伸びていくのだと思います。
「子育て」をしてて、思わず怒ってしまったとき、子どもを悲しませてしまったとき、自分を責めていませんか?
そこからの”学び”は必要ですが、必要以上に自分を責めないでくださいね。
「自分を責める気持ち」は、地面には吸収されず流れていきます。
大地の根っこには「自分を好き」だという”お水”が必要です。
・・・・・最近、ちょっと乾き気味?かな(・・・)
カテゴリーを見て、「何だこれは?」って思われた方も多いと思います。
もちろん造語ですが、意味があります。
そのまま読むと「地面を育てる」
これだけでは、ますます何のことかわかりません。
「地面」って、大地のことです。
自分がしっかり立つ足元です。
「子育てしながら、自分も育ち、そして、自分の足元しっかり固めて、子どもや自分にどんな嵐が来ようと倒れない強い根元を作る」
・・・・そんな意味が込められています。
私はとても弱い木でした。
夫という支木がなければ、一人で立っていられない依存心の強い木でした。
「子育て」も、二人でしている間はあまり不安はありませんでした。
ある日急に支木が外れた瞬間、いろんな嵐がやってきたのです。
私は子どもがある程度の年齢になっていましたが、これがもし、子どもが生まれてすぐだったら、子どもがまだ小さかったら。。。と思うと、どんなに心細く、不安になるか。。。思っただけで胸が痛みます。
「大地にしっかり立つ」ために大切なこと。。。それは「自分を好きになること」
どんな自分も、全て「ありのまま」受け入れることができて、初めて大地の根っこは奥深く伸びていくのだと思います。
「子育て」をしてて、思わず怒ってしまったとき、子どもを悲しませてしまったとき、自分を責めていませんか?
そこからの”学び”は必要ですが、必要以上に自分を責めないでくださいね。
「自分を責める気持ち」は、地面には吸収されず流れていきます。
大地の根っこには「自分を好き」だという”お水”が必要です。
・・・・・最近、ちょっと乾き気味?かな(・・・)


